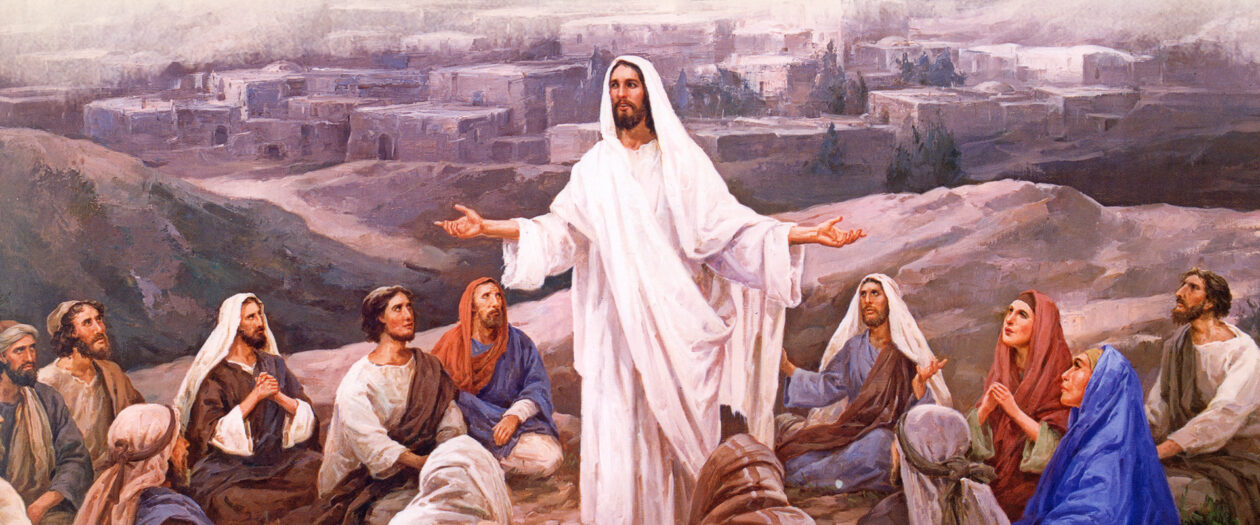「御言葉を行う人になりなさい」 ヤコブの手紙1章22-25節
津村春英牧師
ある調査によると、2023年の初詣に行くと、6割が回答したそうです。人は無病息災、商売繁盛、家内安全を祈願します。これは健康、お金、家族のことです。皆が幸いを求めているのです。
ヤコブ書に「幸いな人」について書かれています。それはどういう人でしょうか。まず、「御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わる者になってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去ると、それがどのようであったか、すぐに忘れてしまいます。」(1:22-24)とあります。当時の鏡は銅の合金製で、像は小さく、不鮮明だったと思われます。
他方、「しかし、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れずにいる人は、聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人になります。このような人は、その行いによって幸いな者となるのです」(同25聖書協会共同訳)とあります。下線部「一心に見つめて」の原語は「見ようとしてかがむ、のぞき込む」を意味し、御言葉という鏡に自分自身を映して見ることにより、何をすれば良いかを教えられ、行う人になり、幸いへと導かれるのです。